[旅の日記]
千住宿から吉原 
 東武鉄道でやってきたのは「北千住駅」です。
東武鉄道でやってきたのは「北千住駅」です。
JR常磐線、東京メトロの日比谷線と千代田線、つくばエクスプレス、東武鉄道が集まるターミナルです。
古くは日光街道や奥州街道の宿場として栄えてきました。
 今日はその宿場町を巡ってみます。
今日はその宿場町を巡ってみます。
西口に出ると、駅前ロータリーはルミネと丸井の近代的なビルに囲まれています。
とても昔の千住宿があったところだとは考えられません。
その丸井の横を通るミルディス通りを、北に向かって歩いていきましょう。
駅前の賑わいから少し離れて、夜になると人が集まる飲み屋街「毎日通り飲食店街」の看板が挙がっています。

小さなお堂があります。
「めやみ地蔵尊」で、その隣には新義真言宗の「長圓寺」があります。
江戸時代初期、出羽国湯殿山の行者の雲海によって開山されました。
境内には魚籃観音が安置されています。
 その先には「千住氷川神社」もあります。
その先には「千住氷川神社」もあります。
素戔嗚尊を主祭神とする神社です。
先ほど訪れた「長圓寺」の魚籃観音は元々この「千住氷川神社」にあったのでしたが、明治時代の神仏分離で移されたものです。
1307年に下総国千葉氏が、牛田に氷川社を創建したのが始まりです
1910年に隅田川の洪水を防ぐために住町北側に荒川放水路を構築したのですが、その時に氷川柱をこにに移して今に至っています。

ここからは1筋西に移動し、旧日光街道に進みます。
旧日光街道との角にある公園は、桜が満開です。
ソメイヨシノに混ざって赤い花をつける桜の木があり、その花の色が鮮やかです。
待ちゆく人が、自転車を止めてスマホで写真を撮っています。
 道の反対側には、古民家を活かしたお茶とかき氷の店もあります。
道の反対側には、古民家を活かしたお茶とかき氷の店もあります。
ここで少しだけ北側、つまり日光方向に足を進めます。
旧街道の街道沿いだけあって、趣のある立派な家が今も残っています。
 そんな街並みを眺めながら辿り着いたのが、「名倉医院本院」です。
そんな街並みを眺めながら辿り着いたのが、「名倉医院本院」です。
「骨接ぎと言えば名倉」と関東一円で有名な名倉医院です。
日光街道や水戸街道の分岐点も近く、駕籠や大八車で来る患者で溢れていました。
秩父の畠山家の末裔で千住に移り住み、1770年に名倉名前賢が接骨院を開業しました。
1848年の母屋や長屋門が、いまも残っています。

それではここで旧日光街道を引き返して、南に向けて歩いてみます。
「宿場町通り」の商店街が続きます。
この「宿場町通り」ですが、けっこう混みあっています。
 そんな中で人気の団子屋があります。
そんな中で人気の団子屋があります。
餡のかかったみたらし団子が、見るからに美味しそうに並んでいます。
思わず頼んでしまいました。
解けるような柔らかい餅に、甘じょっぱいたれが絡んでおり、ホッとする一瞬です。
串を片手に、さらに南に進みます。


北千住駅から出る千住駅前通りを越えたところに、「勝専寺」があります。
勝専寺赤門が門を閉ざしており一瞬ひやりとしましたが、横の勝手口から境内に入ることができます。
「勝専寺」は1327年に新井図書政次が荒川に仕掛けた網にかかった千手観音像を見つけたことから、この地を千手と呼びました。
 子の新井兵部政勝によって観音像は安置されることになりました。
子の新井兵部政勝によって観音像は安置されることになりました。
正面には本殿、そして左手前には馬頭観世音堂があります。
この馬頭観世音堂にあるのが閻魔像です。
北千住はここまでです。
翌日は北千住から日比谷線に乗り三ノ輪まで移動します。
あいにくの雨で、おまけに15度ほども気温が下がる寒い1日です。
 「三ノ輪駅」で降り、土手通りを南に進みます。
「三ノ輪駅」で降り、土手通りを南に進みます。
しばらく進むと見えてきたのが「あしたのジョー像」です。
 「あしたのジョー」の舞台となったこの辺り、いわゆる「山谷のドヤ街」にちなんで建てられました。
「あしたのジョー」の舞台となったこの辺り、いわゆる「山谷のドヤ街」にちなんで建てられました。
江戸時代の木賃宿からきた街の雰囲気は、昭和の高度経済成長期では日雇い労働者の街に変貌しました。
いまでも少し東側に足を踏み入れると、ごみごみした街が広がっています。
「あしたのジョー像」から少し進んだところに、「見返り柳」があります。
吉原遊廓の入口で、吉原で遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いに引かれ振り返ったところです。
ただしここにある柳の木は、昭和になって植えられたものです。


さてS字に曲がった五十間道の先に、「吉原大門」があります。
道が曲がっているのは、大門の前まで行かないと吉原の様子がうかがえないようにするためです。

 そして当時は黒塗りのアーチ門であった「吉原大門」の跡には、名前を記した柱が建っています。
そして当時は黒塗りのアーチ門であった「吉原大門」の跡には、名前を記した柱が建っています。
吉原は碁盤の目状に整備された造られた一角で、周りは塀で囲まれ入口はこの1箇所だけでした。
これは吉原に売られたり集まってきた遊女が、外への逃亡を防ぐためです。
それでは今も残る碁盤の目の区画と、その中央を貫く仲之町通りを歩いてみます。
1984年に風俗営業取締法が大幅に改正されましたが、周りにはいまでも風俗店が連なっています。
江戸幕府が日本橋葺屋町(現在の日本橋人形町)に吉原遊廓を開きます。
ところが、1657年の「明暦の大火」で焼失してしまいました。
 そこで新たに移転したのが、いまの場所です。
そこで新たに移転したのが、いまの場所です。
日本橋葺屋町を元吉原、台東区千束を新吉原と呼んで区別します。
仲之町通りには、観光用に造られた蔦屋重三郎が開いた書店があります。
 その先にあるのが「吉原神社」です。
その先にあるのが「吉原神社」です。
1872年に吉原の四隅にあった稲荷祠を、そして1935年には遊廓に隣接する吉原弁財天が、次々と合祀されてできました。
吉原遊廓の鎮守として慕われてきました。
それではここから京町通りを歩いて、再び「三ノ輪駅」方向に戻ります。
 しばらく進むと公園があり、そこに石碑があります。
しばらく進むと公園があり、そこに石碑があります。
「一葉記念公園」で、その向かいには「一葉記念館」があります。
樋口一葉が住居を構えた場所のひとつです。
「たけくらべ」「にごりえ」で有名な小説家です。
1872年に東京府第二大区(現在の東京都千代田)で生まれた奈津は、4歳で公立本郷小学校に入学します。
 しかし幼少のためにほどなく退学し、半年後に再び私立吉川学校に入学します。
しかし幼少のためにほどなく退学し、半年後に再び私立吉川学校に入学します。
このころから読書を好んでいたといいます。
1886年には上中島歌子の歌塾「萩の舎」に入門します。
しかし一葉の生活は、必ずしも豊かなものではなかったのです。
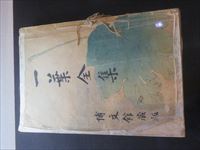
 作家の収入も少なく、質屋通いを余儀なくされました。
作家の収入も少なく、質屋通いを余儀なくされました。
一時は作家の仕事を諦め下谷龍泉寺町に荒物と駄菓子を扱う雑貨店を開きます。
しかし近くに同業者が店を開いたため売り上げは落ち、商売はうまくいきません。
再び文壇に戻り、1896年に文藝倶楽部に「たけくらべ」が掲載され、世間の目に留まるようになります。
しかし24歳に肺結核で死去するという不遇の人生でした。
「一葉記念館」では、そんな一葉の一生を知ることができます。
昨日、今日と宿場町の千住そして吉原遊廓をみてきました。
まだまだ東京には隠れた歴史がたくさんあることを知ったのでした。
旅の写真館(1)

東武鉄道でやってきたのは「北千住駅」です。
今日はその宿場町を巡ってみます。
その先には「千住氷川神社」もあります。
道の反対側には、古民家を活かしたお茶とかき氷の店もあります。
そんな街並みを眺めながら辿り着いたのが、「名倉医院本院」です。
そんな中で人気の団子屋があります。

子の新井兵部政勝によって観音像は安置されることになりました。
「三ノ輪駅」で降り、土手通りを南に進みます。
「あしたのジョー」の舞台となったこの辺り、いわゆる「山谷のドヤ街」にちなんで建てられました。


そして当時は黒塗りのアーチ門であった「吉原大門」の跡には、名前を記した柱が建っています。
そこで新たに移転したのが、いまの場所です。
その先にあるのが「吉原神社」です。
しばらく進むと公園があり、そこに石碑があります。
しかし幼少のためにほどなく退学し、半年後に再び私立吉川学校に入学します。
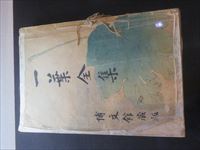
作家の収入も少なく、質屋通いを余儀なくされました。