[旅の日記]
軍港横須賀とペリーの久里浜 
 本日の散策は、京浜急行の横須賀中央駅からのスタートです。
本日の散策は、京浜急行の横須賀中央駅からのスタートです。
軍港の横須賀、そして久里浜ではペリーの来航の軌跡を追います。

 横須賀中央駅から海側に15分ほど歩くと、「三笠桟橋」があります。
横須賀中央駅から海側に15分ほど歩くと、「三笠桟橋」があります。
ここから要塞の島「猿島」への船が出ているのですが、「猿島」への訪問は他の日に譲り本日はその隣の「三笠公園」を訪れます。
「三笠公園」とはその名の通り、戦艦「三笠」が復元・保存されています。
「三笠」とは大日本帝国海軍の戦艦で、奈良県にある三笠山(若草山)にちなんで名付けられました。
イギリスのヴィッカースに発注して建造され、1900年に進水しています。
軍事強化のために戦艦を6隻、装甲巡洋艦を6隻配備する計画の最終艦で、バロー・イン・ファーネス造船所から横須賀に入港・整備後に、舞鶴を本籍港として活躍します。
 特に1904年から始まった日露戦争では連合艦隊旗艦を務め、圧倒的な勢力をもつロシアのバルチック艦隊に日本海海戦で大勝します。
特に1904年から始まった日露戦争では連合艦隊旗艦を務め、圧倒的な勢力をもつロシアのバルチック艦隊に日本海海戦で大勝します。
その時の連合艦隊の司令長官が、東郷平八郎です。
しかし日露戦争終結直後の1905年に、佐世保港での爆発事故で沈没してしまいます。
修復された「三笠」は、第一次世界大戦にソ連を責めるためのシベリア出兵支援にも参加しています。
しかしワシントン軍縮条約によって、「三笠」は廃艦が決定してしまいます。
折しもこのころ発生した関東大震災で岸壁に衝突して浸水し、帝国海軍から除籍されてしまいます。
 解体される予定だった「三笠」ですが、根強い保存運動が起こり復帰できない状態にすることを条件に保存されることが決まります。
解体される予定だった「三笠」ですが、根強い保存運動が起こり復帰できない状態にすることを条件に保存されることが決まります。
「三笠」は横須賀に移され、周りをコンクリートで固められてしまいます。
第二次世界大戦の敗戦後は再びソ連に解体されそうになりますが、今度はソ連に対して反共を掲げたアメリカに阻止され一命を取り留めます。
しかし甲板上の船室・砲弾は取り除かれ、甲板には水族館やキャバレーが造られて、三笠の面影はすっかり消えてしまいます。
三笠が今の姿に戻るのは戦後に再び起こった復元運動が叶ったからで、「記念艦三笠」としてマストや砲弾がコンクリートで再現されています。

ここから西へ、1kmほど歩いて行きます。
この辺は自衛隊とアメリカ軍の施設が入り組んでおり、カメラを向けると監視員が飛び出してきます。
あわててシャッターを押していた指を放したのですが、監視員は撮った写真を見せろと詰め寄り、カメラを操作して写真が撮られていないことを確認して初めて引き下がって行きます。
基地内を外から眼で眺めることは許されているのに、写真ではどこが違うのかは理解に困るところですが、ややこしい国際情勢に飲み込まれないように歯向かわないことにします。
京浜急行「汐入駅」近くには、横須賀海軍めぐりの汐入ターミナルがあります。
平日だと言うのに乗船待ちの人でいっぱいです。
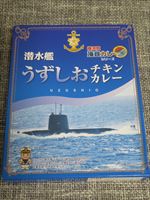
 かろうじて次の便の乗船券を手に入れることができたのでした。
かろうじて次の便の乗船券を手に入れることができたのでした。
横須賀海軍めぐりは、遊覧船で横須賀港の海上自衛隊、アメリカ海軍の戦艦を見て回る45分のツアーです。
まず最初に目にするのは、初めて見る潜水艦に胸が躍ります。
 数えてみると4隻ほどの潜水艦が、水面から頭を出しています。
数えてみると4隻ほどの潜水艦が、水面から頭を出しています。
見えていたのは自衛隊のものばかりです
次に目の前に現れるのは183番を船体につけた自衛隊の護衛艦「いずも」で、ヘリコプターが搭載可能な船です。
その先には、アメリカ海軍のイージス艦の「マスティン」と「カーティス・ウィルバー」、そしてその後ろにも数隻が並んで停泊しています。
戦艦の多さに圧倒されます。
その先遠くに、巨大な船があります。
昨日入港したばかりのアメリカ軍空母の「ロナルド・レーガン」が、積み荷を降ろしているところです。
行き先を知らされない空母にこの場に出くわしたということは、なんという幸運なのでしょうか。
太平洋艦隊所属のニミッツ級航空母艦で、レーガン大統領にちなんで名づけられた空母です。
原子炉2基を有する原子力空母で、もちろん甲板には戦闘攻撃機が配備されています。
全長が333mですから、東京タワーを横に寝かせた長さがあります。
遊覧船から見て回るのですが、最初に目にしてからなかなか反対側面に辿り着けず、いかに大きな船なのかが判ります。






 掃海母艦の「うらが」と、掃海艇「ちちじま」の親子船艇も停泊しています。
掃海母艦の「うらが」と、掃海艇「ちちじま」の親子船艇も停泊しています。
この日は「うらが」と「ちちじま」が何かの理由で船首を逆にして停まっており、この姿はなかなか見ることができないと言うことです。
その次には、機雷除去のための掃海艦「つしま」と「はちじょう」も停泊しています。
磁石を持った機雷が鉄の船底にのようなくっ付いてこないようするため、木で造った船です。
ひょっとするとこれが最後の木造船となるのかもしれません。
 船首に巻き揚げようのローラを備えた海洋観測艦「にちなん」と「わかさ」もいます。
船首に巻き揚げようのローラを備えた海洋観測艦「にちなん」と「わかさ」もいます。
マイクロ波などを使い海底の地形や潮流を測定することを目的とした船で、測定したデータは軍事用として使われるため我々の目に触れることはありません。
遊覧船は横須賀湾にできた島と本土との間を進みます。
元々陸続きだったところを軍事格納庫とし、さらに上空から発見されないように常緑樹の木々に植え替えられました。
その後弾薬の火災爆発が横須賀の他の施設に炎上しないように、つながっていた陸地を手作業で掘り進めて島にしてしまいました。
 そんな苦労して掘ったところを、船は進んで行きます。
そんな苦労して掘ったところを、船は進んで行きます。
わずか45分の湾内の小旅行でしたが、知らない世界を見てしまったという印象を受けたのでした。
さてここからは、電車で久里浜に移動します。
駅から1kmほど離れたところの久里浜港に近くにある「ペリー公園」に寄って行くことにします。
公園には幕末の混乱期にペリーが上陸した碑が建っており、周りの広場ではそんなこと関係ないとばかりに子供たちが平和に遊んでいます。
公園内にはひときわ目立つ洋館の「ペリー記念館」があり、開国を迫るペリーと幕府との駆け引きの様子が映像と資料で展示されていました。
 「ペリー公園」から京浜久里浜駅までブラブラしながら戻ってくると、久美浜で唯一の天満宮があります。
「ペリー公園」から京浜久里浜駅までブラブラしながら戻ってくると、久美浜で唯一の天満宮があります。
本日は軍事施設の堅い話ばっかりでしたので、神様を見てなぜかホッとしてしまい、ちょっと寄り道をすることにします。
こうして、戦乱の日本と現在の自衛のための軍事活動を見終えて、本日は帰路についたのでした。
旅の写真館(1)
(2)

本日の散策は、京浜急行の横須賀中央駅からのスタートです。

横須賀中央駅から海側に15分ほど歩くと、「三笠桟橋」があります。
特に1904年から始まった日露戦争では連合艦隊旗艦を務め、圧倒的な勢力をもつロシアのバルチック艦隊に日本海海戦で大勝します。
解体される予定だった「三笠」ですが、根強い保存運動が起こり復帰できない状態にすることを条件に保存されることが決まります。
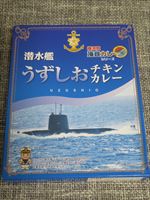
かろうじて次の便の乗船券を手に入れることができたのでした。
数えてみると4隻ほどの潜水艦が、水面から頭を出しています。




掃海母艦の「うらが」と、掃海艇「ちちじま」の親子船艇も停泊しています。
船首に巻き揚げようのローラを備えた海洋観測艦「にちなん」と「わかさ」もいます。
そんな苦労して掘ったところを、船は進んで行きます。
「ペリー公園」から京浜久里浜駅までブラブラしながら戻ってくると、久美浜で唯一の天満宮があります。